この記事は アドベントカレンダー2023 の7日目の記事です。URL先の一覧からぜひ他の人の記事も見てみてください!
もくじ
-
はじめに
-
毎日創作することのメリット
-
毎日創作創作を実際に100日続けてわかったこと
-
最後に
はじめに
こんにちは、23Bの熱野頂点(飛ぶ人)です。普段は毎日1枚ドット絵を描いていて、最近連続100日目を突破しました。
今回の記事では、「毎日創作をすることの偉大なパワー」 と 実際に100日連続で描いてわかったこと について語ります。
毎日創作することのメリット
創作物の質が上がる
毎日続けることで少しずつですがその創作の実力は向上しやすいです。ただし、普通言われるような実力の上昇である「作品のクオリティの最大値の向上」というよりも 「最低限出せるクオリティの向上」 というイメージのほうが強いです。
もちろん作品を 毎日一つ完成させる のではなく少しずつ進捗を生むスタイルを取ったり一日に絵にかけられる時間が多ければ実力の最大値の向上も見込めます。しかし、 毎日一つ完成させる 場合は「短時間で描けるものはここまで」というラインがじわじわと上がっていくようなイメージで実力がついていきます。
例えば、描く速度が上がることで実質的に一枚にかけられる時間が増えて絵のクオリティも上がったり少しずつ色使いを覚えて作品の色合いが良くなったりするなどの変化が徐々に現れてきます。一日で得られる進歩は大きくありませんが何日も積み重ねれば質は良くなっていきます。
創作が習慣化する
一日のうちに何とかして創作する時間を作るうちに自然と生活の一部に作品と向き合う時間は増えていきます。
例えばTwitter(新X)を無意味にいじる時間、YouTubeをダラダラ見る時間、移動時間で暇な時。生活の中にはなくなったほうが幸せになれるものがたくさんあります。それらを創作の時間の力で全て消し去ります。
そうすれば「毎日絵を描きたいのに時間が無い」と言っている人たちも30分くらいは時間が取れるようになっていくはずです。
習慣化することの利点は、「いざ大きい進捗を生もうと決心したが手が動かない…」という状況を減らすことができます。毎日進捗を生む習慣をつけておくことで頑張ろうと思ったタイミングでちゃんと頑張ることができます。 正直実力なんかよりもこっちの方がよっぽど大きいメリットです。
創作にかかる時間を把握できるようになる
さて、皆さんは自分が一作品にどのくらい時間をかければどのくらいの物が出来上がるか、という感覚を持っていますか?この感覚は創作の場数を踏まなければなかなか養うことができません。締切付きの作品を完成させるために徹夜する…なんて人は特に普段の創作から意識して身につけていくべきです。
毎日創作し続けると特にこの感覚は身に付きやすいと思います。なぜなら、忙しく創作に時間をあまりかけられない日などで「短時間で仕上げた作品」を作る経験を、休日などの時間をたっぷりとれる場面で「それなりに時間をかけた作品」を作る経験を積むことができ、この感覚を身に着けるには持って来いの環境です。
不定期にやるよりも進捗が生まれやすい
この記事をここまで読んでいて作品に向き合う間隔が不定期だけど時間があるときに一気に進捗を生み出したいというそこのあなた!残念!私は 不定期で一気に進捗を生むという行為はまったくお勧めできない という思想を持っています!理由は二つあります。
一つ目の理由は 「創作に触れない期間が長くなってしまうから」 です。残念ながらどんなに上手い人でも一、二ヶ月したら実力が落ちてしまいます。大きい創作でなくとも定期的に筆を握らなければ人間は愚かなのでダメになってしまいます。
「時間ある時に絵描きたいな~」 ←いつまでたっても描き始めずに容赦なく二か月くらい経ちます。 不定期にやって長い期間があいてしまうくらいなら少しでも毎日筆を握ってみてはいかがでしょうか。
毎日創作創作を実際に100日続けてわかったこと
少しずつだが実力の向上を感じた
80日目辺りから、以前までの絵よりも少しずつ絵が全体的に良くなってきているなと感じ始めました。実際に下の二枚の絵は同じくらいの時間をかけた食べ物のドット絵です。
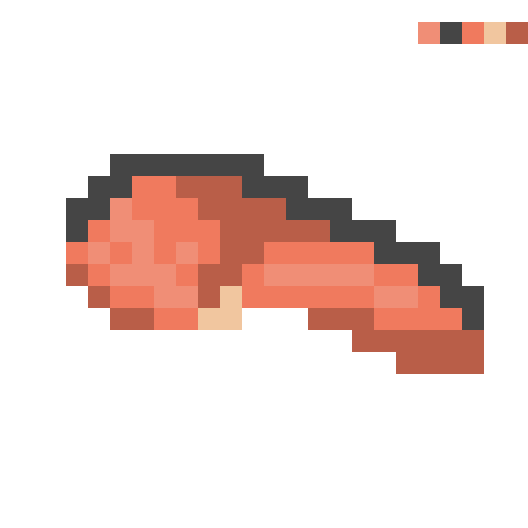
↑52日目「鮭」

↑109日目「たこ焼き」
この絵の成長を語るためにいくつかドット絵特有の概念について説明します。
まず、ドット絵にはピクセル(ドット)という概念があります。これはドット絵を構成する四角の点のことです。
次に、絵のサイズという概念があります。これはピクセル(ドット)が何個敷き詰められているかを表したもので、例えば16×16や48×48などがあります。
52日目から109日までに起こった変化は 「サイズを大きくしてもそれなりに短い時間で描けるようになったこと」 、 「色使いが上手くなった」 ことの二つです。
前者のサイズに関しては実際に鮭の「24×24」からたこ焼きの「48×48」に大きくなりました。ドット絵を描いてみるとわかりますが24×24は計576ピクセル(ドット)なのに対し48×48は計2304ピクセル(ドット)と打つドットの数は4倍になります。つまり一枚にかかる時間はサイズが大きいほうがより時間がかかるということになります。しかし、毎日描き続けた影響で自然と筆が早くなりよりサイズの大きいドット絵を一日の内に描けるようになりました。
後者の色使いに関しては資料を見てより適切な色を選べるようになったという点が大きな成長です。鮭よりもたこ焼きの方が明度が高い色が使われ、質感も色相の変化を上手く活用し明度を下げないように工夫されています。これにより食べ物としてよりおいしそうに見えるたこ焼きを描けるように成長しています。
締切に追われる感覚が消えた
50日チャレンジと称し夏休み中にやっていたときはまだまだ一日の終わりという締切に追われながら描いているという感覚がありました。しかし70日を超えたあたりからその感覚はよほど忙しい日でない限りは湧いてこなくなりました。
これには二つの要因があると考えています。
まずは 「習慣化したことで慣れたこと」 が挙げられると思います。毎日追われ続け常に頭に進捗の事がよぎり続ける限界の日常を繰り返したことでシンプルに慣れました。一見根性論のように聞こえますが、なんとびっくり根性論です。ただ、根性でも力にはなっているのでなれって怖いなあとも思います。
もう一つは 「自分が一つ作品を作るためにかかる時間を把握できるようになったこと」 が考えられます。メリットの項でも解説しましたが自分がどのくらいのクオリティなら限られた時間で描けるかが100日分の経験が教えてくれるようになります。これにより締切に追われるような感覚はなくなりこのくらいの時間ならこのくらいの作品が作れるだろうという感覚が掴めるようになりました。
別のことを創作を並行してできるようになった
51から100日の間にはtraPとして制作する冬コミの画集の絵を描くこと、他のサークルのイベント、期末試験など毎日進捗以外のタスクが非常に多かったです。しかし1から50日の頃の毎日進捗で手一杯の日々とは違い、単純に筆が速くなったことで絵以外のタスクにも時間を回せるようになりました。特に、毎日進捗の習慣化のおかげで期末試験期間などハチャメチャに忙しい期間でも一日一作品は必ず書くという意識を持てるようになりました。
これからの人生において生活との両立が十分可能な趣味を獲得できたのは個人的に良いことだなと思っています。
描けるものが増えてかなり楽しくなった
1 ~ 50日の間には「ネタは思いついたけれど画力が足りず描けない」という事態が多発していました。しかし、51 ~ 100日の間に再チャレンジしたところ描けるようになっているもの増えていました。
描けないが描けるに変わったとたんに絵はとても楽しいものになりますしネタ切れに悩むことも少なくなりました。まぁ今でもたまに悩むことはあるんですけどね。自分の描けるものがだんだん明確化されていく中で描けないものも浮き彫りになってきたので今後挑戦したいと考えています。
最後に
いかがでしたか?毎日絵に向き合っていれば初心者でも少しずつなら上達するのだなあと思いました。
私のブログはここで終わりですが、 アドベントカレンダー2023 はまだまだ続きます!夏鈴さんの記事も是非とも見てみてください!
明日の記事はいくらはむさん、ramdos君の記事の二本立てです!お楽しみに!
