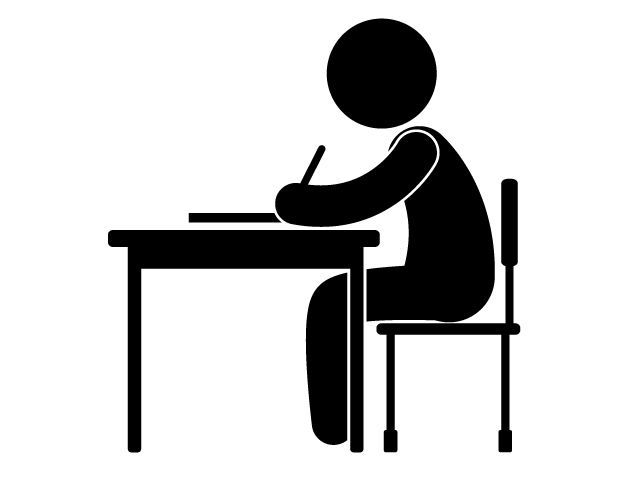はじめに
これは2018新歓ブログリレーの4/11の記事です。
新入生の皆様初めまして。masutech16ことますぐれと申します。traP内ではプログラマをやっています。
さて、今日のテーマはタイトルの通りです。とはいっても、東工大に入学した人に対して勉強法を伝えたところでという感じですよね。自分よりも良いメソッドを持っている人はたくさんいるでしょう。
今日お伝えしたいのは勉強の仕方ではなく、大学生という身分を利用して興味関心を伸ばし、充実した大学生活を送るための簡単なTipsのようなものです。
せっかく大学に入学したのですから興味のあることをたくさん勉強したいですよね? 時間がない!という幸せな悲鳴に包まれながら4年間を過ごしたいですよね? この記事はそういう人に向けたものになっております。
それでは早速本題に参りましょう。
1.時間を有効利用しよう
大学生は暇だ、という言説をどこかで聞いたことがあるかと思います。しかし、現実は非情で以前よりも時間が無くなることが多いです。(ちなみに学年が上がるとどんどん忙しくなります)
そのため、何かを学ぶのにおいては時間の使い方がより重要になっていきます。まずは時間をうまく使うための方法をいくつか見ていきましょう。
講義に出る
ぼくは1年の頃は出席がないとわかるとすぐに講義に行かなくなるタイプの人でした。教科書を読んで独学で進めようと思っていたためです。
これは思考力を鍛えるという意味ではとてもよかったのですが、講義の2倍くらいの時間を使っても講義の内容を追いきれないことも多く、時間効率的にはあまりよくない戦略でした。
講義中しゃべっている先生はその分野にとても精通しています。難しい内容についてはその人の話を聞いたほうが格段に理解しやすいと思います。講義中に内容を理解すれば復習は容易でしょう。
ただ、教科書を独学で進めるというのはすごく力になります。授業以外で自分の興味のあるジャンルの教科書を読んでみるのは悪くないと思います。が、これももう少しいい方法があります。(後ほど紹介します)
人の話を聞く
自分の知らないことを知っている人の話を聞くと、自分を豊かにしてくれる未知のジャンルの扉を開くことができます。
様々な概念を知っているだけで学習効率が格段に良くなります。これはアナロジーが効くようになるためです。
というわけですし、たくさんの概念に出会いたいですよね。しかし存在すら知らないことを調べるのはほぼ不可能なので、新たな概念とはゲリラ的に遭遇するほかありません。
では遭遇頻度を上げるにはどうしたらよいでしょう。それには強い人の話を聞くのが効率的です。先輩でも教授でも外部の人でも構いません。とにかく、自分が知らない知識を持っていそうな人の話を聞く機会を増やしましょう。
ところで、4/13(金)の17:00よりtraPが主催するLT会がW531であるようです。LT会とは個人が自分の好きなことや興味のあることについて10分~20分程度のプレゼンをする会です。早速の未知との遭遇を実践できるチャンス、突撃してしてみてはいかがでしょうか?
2.最初から興味を絞らないでいよう
これは題目で言いたいことはほとんど終わっているのですが、どの系に進むにせよ、1年のうちは様々な分野にアンテナを張ることをお勧めします。以下に理由を記します。
私たちは専門で何を学ぶか実はよく知らない
これが一番の理由です。○○が学びたくて入ったけど、実はそこでやってることは□□的な内容だった……。みたいなことがあったら人生を棒に振りかねません。専門を選ぶというのは正直大学選びよりも重要なことです。
ここで変な意地を張って当初の志望を通すよりは、最初からいろいろな選択肢を見る方が良いと思います。転類も視野に入れつつ所属したい系を探すとミスマッチすることはまずないでしょう。文転したいと思ったらさすがに厳しそうですが……。
知らないことは選択できない
上で書いたことと少しかぶるのですが、自分の知らないことは自分の中の選択肢として存在しません。
せっかくならすべての分野で何をしているのかを一通り知ってから系所属をしたくありませんか? 所属してから隣の芝が青い状態になっても悲しいだけです。知る前に興味ないと決めつけず、少しだけでもいいのでその分野で何をするのかを知りましょう。
具体的には各系のシラバスを見るのをオススメします。
3.環境を変えよう
何かを学ぶ上で環境というものは非常に重要です。周りの人が一心不乱に何か好きなことを突き詰めている場所にいたら、自分も何かしなくては! と思えてきませんか? 人間はどうしても楽な方に逃げてしまう生き物なので、環境を整えてモチベを維持するのは非常に有効な手法となります。
ゼミや勉強会を開いてみる
一人では続かないことも、人を集めれば続くかもしれないーー。ということで、興味のある内容について友達と一緒にゼミをするというのは一つの手です。
例えば数学のゼミだと、教科書を決めてそれを全員で読んでいくというのが標準的な進め方のようです。ゼミの最初にメンバーに担当範囲を割り振り、その範囲について学習してきて順番にみんなの前で発表するというスタイルですね。
勉強会は何かテーマを決め、それに関することを毎日決まった時間に決まった場所で勉強するというのがいいかもしれません。ぼくは今友達と一緒にインフラ系の勉強会を企画しようとしています。
上のほうで教科書を独学するのはいいぞといったのですが、周りに同じ分野に興味のある人がいればゼミを立てたほうが効率的かもしれません。
ちなみになのですが、traP内部では有志で数学系のゼミを行なっています。今は代数くらいしか走ってませんが、前は測度論などもありました。興味があればメンバーを募って立てることもできます。
サークルに入る
自分が大学でしたいことが決まっているのなら、それをするサークルに加入するというのが手っ取り早い環境構築方法です。
当たり前ですが、サークルにはモチベーションが高い人がたくさんいるので、その人たちに囲まれていると自分も自然とモチベーションが上がっていきます。相乗効果も期待でき、お互いにとってwin-winです。
また、活動時間を物理的に作り出せるので、モチベがなくても大きくリズムが崩れなくて済みます。これも人と一緒に活動する上でのメリットになるでしょう。
学びの環境という視点で見たtraP
もうここまで来たら隠さずに宣伝するのですが、traPは何かものづくりをしたいという人にはうってつけのサークルです。
部内SNSでは自分の成果物や進捗状況を上げる場所が用意されており、そこに投稿するとリアクションがもらえます。また、勉強したことを知見としてまとめるwikiや講義ノートなどをリアルタイムで共有できるサービスなども備えています。また、本の貸し借りや相談も活発です。
さらに、これが一番大きいのですが、チズケに閉館近くまで残る人がたくさんいます。自宅に帰るとだらけてしまう、けど帰りたい、というときにチズケに行くとよい刺激をもらえて少しは長く居残れたりします。
技術系・創作系に興味があるのならぜひ一度覗いていただきたく思います。何も知らないけど技術を身に着けたいという方も熱意があれば大歓迎です!
おわりに
少し長くなってしまいました。いかがでしたでしょうか? これからの生活を考える上で少しでも参考になれば幸いです。
明日はNOTORIN君の記事です。お楽しみに!