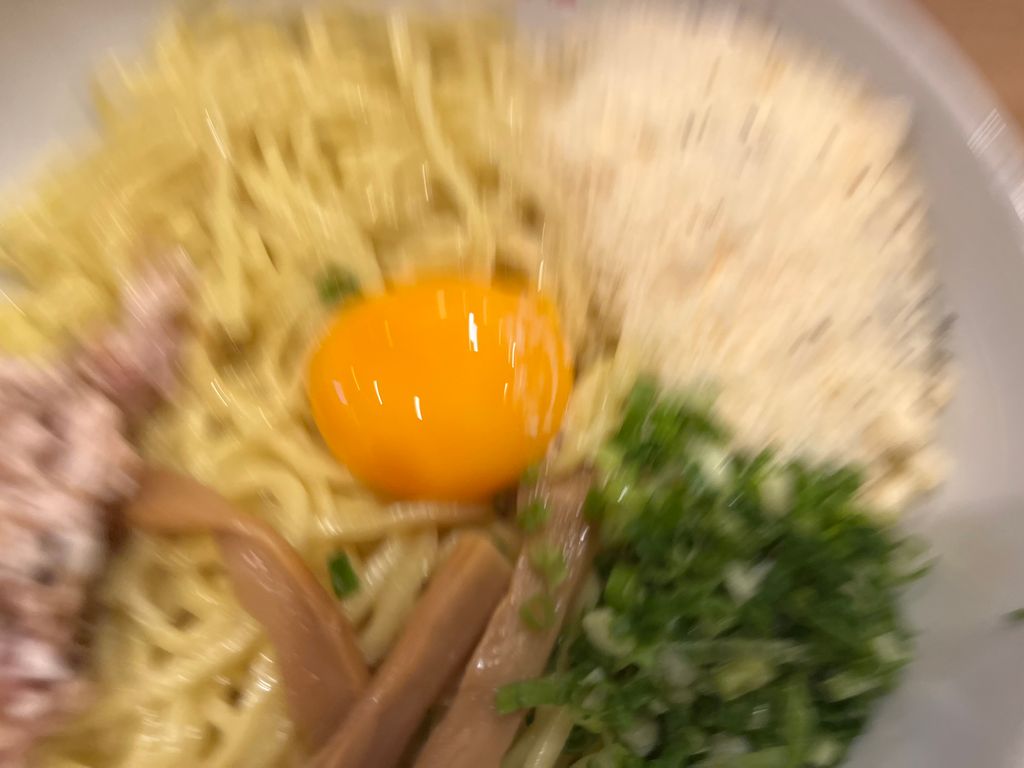この記事は夏のブログリレー8日目の記事です。
みなさんこんにちは、vPhosと申します。普段は曲を作っており、最近BMS制作などもしています。
前提知識
このtraPというサークルでは、個人の知見をサークル全体に共有する手段の一つとして、講習会というものを開く文化があります。
新入生が入部してすぐの5月から7月上旬までの期間は0→1講習会という知識が0の人を1まで押し上げるための講習会が主に開催されますが、それらが一段落すると個人が主催する講習会がぽつぽつと現れ始めます。今年度の例を上げると、
- 新規サービスを作るには講習会
- 100行で作るゲームアクション講習会
- マネジメント講習会 2025
などが個人で開催されました。(抜けてるものがあったらごめんなさい。)
ジャンル別講習会は半分班、半分個人で開催された講習会になります。
ジャンル別講習会って何?
ジャンル別講習会は、個人が持っている作曲技術を班全体に共有しようというサウンド班の講習会です。もともとは個人が作れるジャンルの布教的な側面を考えてこの名前にしたのですが、オーケストラ系などではあまりジャンルなどにとらわれないことが多そうだということ、必ずしも曲を完成させることに重点を置かなくても良いと感じたことなどから、少し実態に合ってない名前となってしまいました。サウンド班の講習会というのもわかりにくいので、命名ミスったかな〜とも感じています。
このブログ投稿時点でUplifting Trance編、UK Hardcore編、シンセサイザー編、耳コピ & 作曲編、Speed Garage編が開催されており、Future Bass編が予定されています。
目的
これまでのサウンド班の01講習会はどんな曲を作るときでも使う普遍的知識を与えるだけに留まっていました。使用ソフトが部内でも7種類ほどあり、作る曲によって重視するポイント、使用する技術などが全く異なってる現状で、統一的で実践的な講習会を開催することは無理があります。そのため、今までは実践的な曲を作り方は個人のリサーチ力に丸投げしていました。これはtraPの班活動の中ではかなり不親切な部類であったと認識しています。
それを解決すべく、YouTubeなどにあるチュートリアル動画のような、サウンド班の各個人が自分の知見を詰めた講習会を開催することで、結果的に網羅的になるようなものを目指しました。
構想から開催まで
元々この構想自体はかなり前(多分去年の新歓期くらい?)からあり、去年の11月頃から動き始めました。
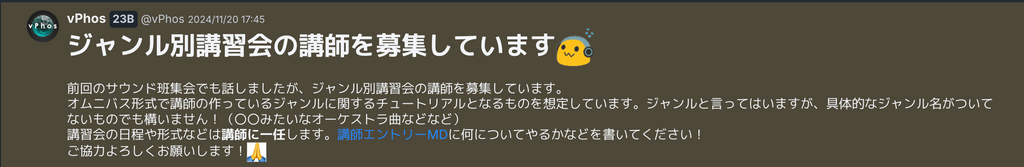
講師を募集しましたので、ここから資料を作っていけば、新歓期に入るまでに開催できそうですね。
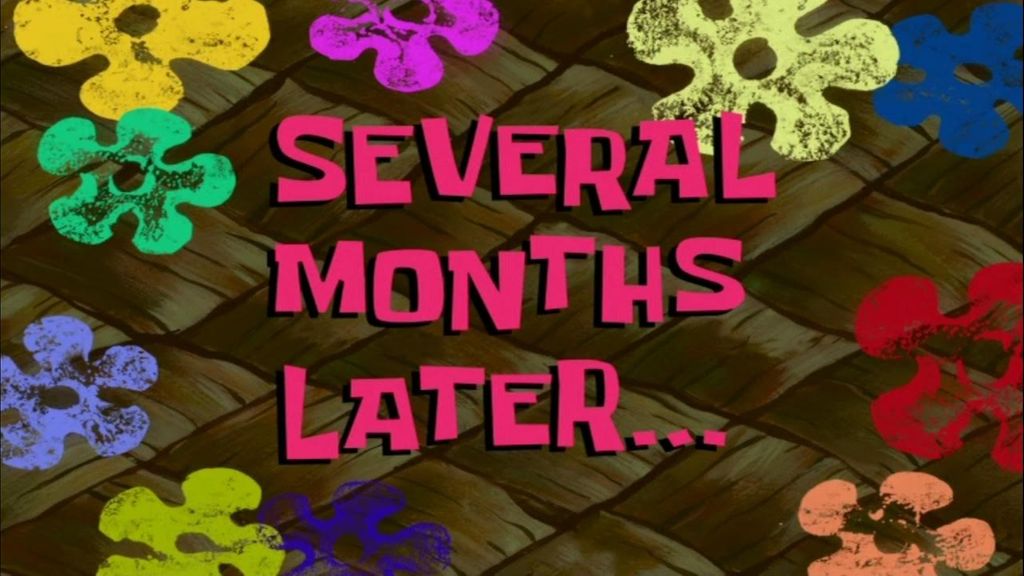
進捗ダメダメです!新歓期入っちゃいました。新歓期終わったらやります。
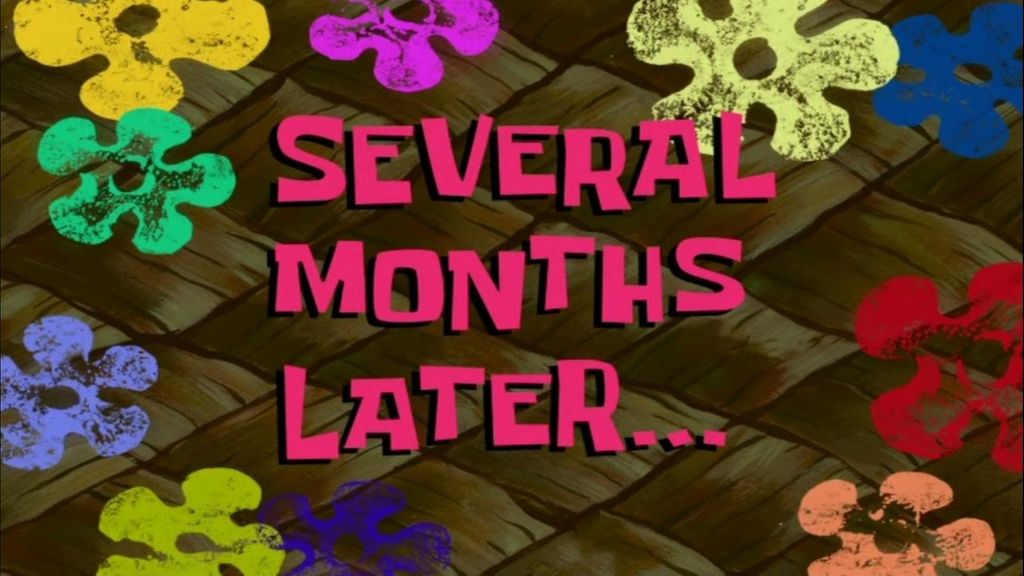
資料作成ダラダラやってたので終わってません……。
こういう新しい取り組みというものは、モチベ駆動だと厳しいんですね。
厳格に締め切りというものを設定しなければ、なかなか完成までこぎつけられません。
というわけで厳格な後輩が無理に締め切りを設定してきました。

持つべきは先輩のケツを叩ける後輩ですね。
そんなこんなで開催することができました。この講習会が次世代のサウンド班員にとって良いものとなり、またこれを引き継いでくれたら嬉しいです。
反省
そもそもジャンルについて説明してない
完全に私の落ち度なんですが、講習会内で例示したとはいえ、ジャンルの全体的な概観を伝えてないせいで、なんかよくわからないけどこれとこれだけは作れる〜みたいな人を生み出してしまった気がします。この辺は来年以降に期待かもしれません。
段取りが悪かった・かかる時間の想定が甘かった
これは私が行ったUK Hardcore編の反省ですが、元々BuildからDropまでで予定していたものが、Dropだけで3時間を超えてしまったため、Buildを作る部分をカットして進めなければいけませんでした。完全初心者を対象と言っても、実際は置いて行きかけてたとも思います。受講者が同時進行で曲を作れるスタイルにしましたが、人によってできる速度に個人差があり、動画やテキスト資料の公開という形態にすべきだったのかもしれないとも思いました。10分ではできないらしい
おわりに
反省は色々ありますが、個人で完結しがちなサウンド班において、交流という意味でも良いイベントになっていると思います。今後も続いてほしいですね。
明日のブログリレーは@toshi00さんです。お楽しみに!!