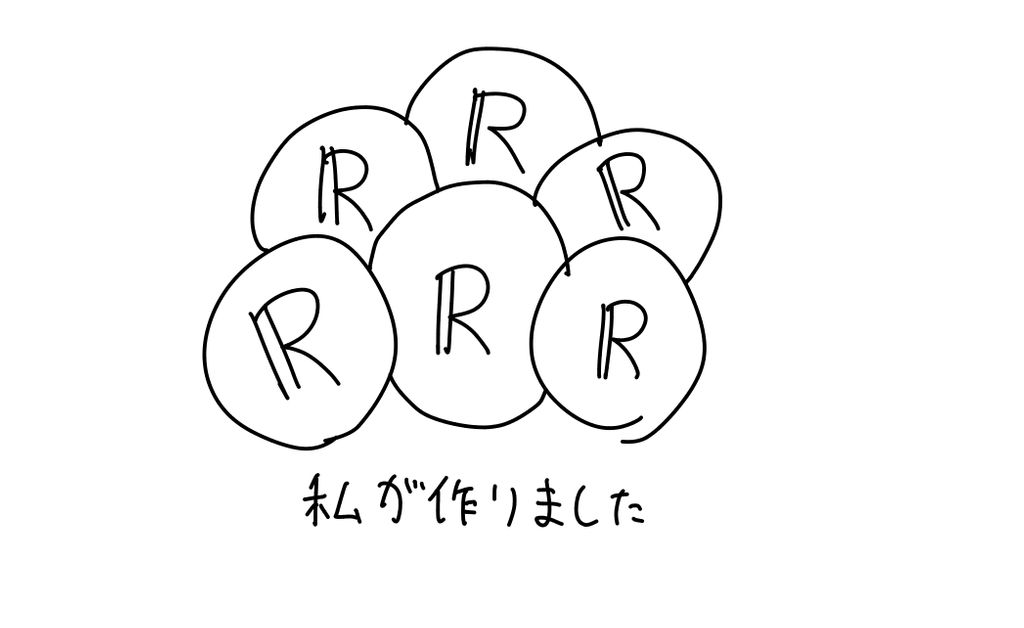この記事は夏のブログリレー2日目の記事です。
「まぁ、好きではじめた仕事ですから」
最近は「そこまで厳密にやる意味あるんですか?」と言われることも増えた。
彼にとっては、その一言が一番こたえる。
まず、素材の入念なチェックから始まる。
集合、公理、順序、距離、連続性。
そのすべてに指を通し、確かめ、磨き上げる。
「やっぱり一番うれしいのは、若い研究者からの感謝の手紙ですね。“あの定義、腹落ちしました”って。やっててよかったなって思います」
「毎日毎日、理論の湿度が違う。時代の空気で“わかりやすさ”ばかりが重視されるけど、定義って、そんな軽いもんじゃないんですよ」
今日は査読論文の提出日。
彼は空集合から丁寧に積み上げた自作の構成法を鞄に詰め、学会へと向かった。
基本的な枠組みは決まっているが、最近の「直観優先」の風潮に合わせて、形式に曖昧さを残さざるを得ないのがつらいところ、と彼は語る。
「冬の仕事はキツイですね。証明も凍りつく(笑)」
「でも、自分が選んだ道だから。後悔はしてないです」
「この定義はダメだ。ほら、条件を一つ緩めるとすぐ破綻する」
彼の目にかかれば、見るだけで定義の骨組みが分かる。
「なぜこの順序性が必要なのか」
「なぜこの完備性にこだわるのか」
それを、誰にも頼らず、自分の手で確かめてきた。
技術立国・数学王国日本、ここにあり。
だが今、一番の問題は後継者不足だ。
「別に、デデキント切断でもいいじゃないですか」
若者のその一言に、彼は言い返す言葉を持たない。
間違ってはいない。ただ、軽いのだ。
かつて実数は、定義することそのものが挑戦だった。
今では、選べるメニューの一項目にすぎない。
30年前は、純粋数学の研究室に多くの“実数職人”がいた。
だが今、本当にゼロから定義する者はほとんどいない。
ε-δの感覚が体に染み込むのに、5年はかかると、彼は語る。
「自分が納得するだけじゃなくて、 読む人に“腑に落ちた”と言わせたい。そのためには、見えない支柱を、一本一本打ち込まないといけない」
「もちろん、出来上がった定義は自分で証明まで全部通してます。そうでないと、愛着が湧かない」
ここ数年は、安価で手軽な直観的説明やビジュアル教材に押されているという。
「いや、ボクはやめませんよ。待ってる人がいますから───」
下町・実数定義の灯火は弱い。だが、まだ消えてはいない。
「時々ね、わざわざメールまでくれる人がいるんですよ。“あの構成法、試験に出ました”って。ちょっと嬉しいですね」
「遠くから会いに来てくれる院生もいる。体が続く限り、定義を磨き続けようと思ってます」
「やっぱりねえ、定義は手ごねなんですよ。いくらAIが進化しても、“なぜそれが成り立つのか”っていうところだけは、人間じゃないと無理です」
1973年、世界が“使える数学”を求め始めた年だった。
定義の厳密さは「重たい」「わかりづらい」と切り捨てられ、
数値解析やモデル化ばかりがもてはやされた。
空集合から一歩ずつ積み上げていく彼の仕事は、
ただの“こだわり”と呼ばれた。
そのとき彼は、一度は筆を折ることを本気で考えたという。
「最近の若い人はすぐ“完成体”に飛びつく。 自然数が“定義されている”ことすら疑問に思わない。
でも、それを乗り越える奴もいる。
ほら、そこにいる斉藤もそう。
“なぜ0は数なのか”を真面目に悩める奴が、これからの数学を変えるんですよ」
最近では、海外の論理学者からも注目されている。
額に流れる汗をぬぐいながら、こう語る。
「本物に追いつき、追い越せ──ですね。定義で世界を変える、っていうのは、夢じゃないと思ってます」
そんな夢を、てらいもなく語る彼の横顔は、まぎれもなく職人のそれだった。
今日も彼は、日が昇る前に作業を始めた。
空集合から始まり、順序対、帰納的定義、等価類、完備化……
明日も、明後日も、その姿は変わらないだろう。
そう、実数職人の朝は早い。
はじめに
皆さんごきげんよう。実数職人のotimaです。この記事ではノイマンの構成から自然数、同値関係により整数、局所化により有理数、そして完備化によって実数を定義していこうと思います。ちなみに以前書きましたが実数の多項式環の剰余環から複素数も定義することもできます。こう羅列してみると商がいかに重要な構成かが見えてきますね。それでは早速定義していきます。
自然数の構成
ペアノの公理
まずは自然数の定義です。ちなみにこの記事では0は自然数です。
この記事を読むような人はご存知だとは思いますがペアノの公理というものがあります。これは自然数を定義する公理、つまり論証なしで正しいと仮定される、議論の前提となる命題です。
その内容はすなわち、
自然数 N という集合、そして次の数を表す後者関数 S という写像があり、以下の条件を満たす。
- 0∈N (始点が存在する)
- 任意の n∈N について S(n)∈N (次の数が存在する)
- 任意の n∈N について S(n)=0 (全体で循環しない)
- 任意の n,m∈N について S(n)=S(m) (Sは単射)
- 任意の E⊆N について 0∈E で n∈E⇒S(n)∈E が成り立つなら E=N (数学的帰納法)
しかし現在一般的に使われているZF公理とは別に自然数のためにわざわざ取り立てて新たな公理を仮定することもありません。実際、ZF公理からペアノの公理を満たす集合を構成することができます。ここではその1つとしてフォン・ノイマンの方法について述べます。
ノイマンの構成法
まず0を用意する必要があります。そこで空集合 ∅ を0とします。空集合の存在はZFから導くことができるので空集合の存在は認めます。そして後者関数 S を、 S(n)=n∪{n} と再帰的に定義します。すると N は、
0:=∅1:=S(0)=0∪{0}={0}2:=S(1)=1∪{1}={0,1}3:=S(2)=2∪{2}={0,1,2}⋮
を要素として持つ集合となります。
このように (次の値)={(前の値の含む要素),前の値} となり、結果としてそれ以前の値全てを含む集合になります。ZFでは無限公理によってこのような、 「空集合を要素として持ち、要素の後者も要素として含む集合」の存在は保証されます。ZFの残りの命題を用いてこのような集合の中で最小のものを作ることができるので、それを自然数の集合とすることができ、これはペアノの公理を満たします。最小のものを自然数の集合としたので、ペアノの公理の5つ目の条件を満たす集合は自然数の集合を部分集合として持ち、外延性の公理により自然数全体の集合と一致します。またペアノの公理を満たせば、それを満たすもの同士の間に関手的な対応が存在するため、このような集合は一意です。
当然自然数には演算も順序もありますから、加法乗法、順序関係を定義します。減法と除法は自然数内ではすべての組に対して定義できないのでのちの範囲を広げた整数、有理数で定義します。以下ではノイマンの構成ではなく一般のペアノの公理を満たす集合について考えます。
ペアノの公理の5つ目の命題と数学的帰納法について
数学的帰納法
ペアノの公理の5つ目の命題が数学的帰納法を表すというのは、示すべき命題を ∀n∈N,φ(n) 、とする時、 E:={n∈N ∣ φ(n)} 、つまり命題を満たす n∈N 全体の集合とする、及び φ(n):=(n∈E) 、つまり n が E に含まれることとする対応により 数学的帰納法の条件と命題5の条件が同値になるためです。
実際、
・ (5つ目の命題)⇒(数学的帰納法)
E:={n∈N ∣ φ(n)} とします。
- φ(0) が真より 0∈E
- φ(k) が真なら φ(S(k)) は真、よって k∈E⇒S(k)∈E
- よって E は5つ目の命題の条件を満たすので E=N 、つまり ∀n∈N,φ(n) が成り立ちます。
・ (数学的帰納法)⇒(5つ目の命題)
φ(n):=(n∈E) とします。
- 0∈E より φ(0) は真
- k∈E⇒S(k)∈E より φ(k)⇒φ(S(k))
- よって φ(n) は数学的帰納法の条件を満たすので ∀n∈N,φ(n) 、つまり ∀n∈N,n∈E
- N⊆E より E=N が成り立ちます。
よりこれらは同値です。
加法
加法は次に整数を構成するのに使うので必須です。
加法も再帰的に定義します。つまり、 n,m∈N に対して、
n+0=nn+S(m)=S(n+m)
と n+(mの次) を (n+m)の次として定義します。すると、
n+0=nn+1=n+S(0)=S(n+0)=S(n)n+2=n+S(1)=S(n+1)=S(S(n))n+3=n+S(2)=S(n+2)=S(S(S(n)))⋮
のように我々の知る自然数の和として機能します。結合性、可換性も成り立ちます。
結合性・可換性の証明
結合性
一般の自然数について何か証明したいならまず数学的帰納法を考えましょう。
まず結合則です。
任意の a,b,c∈N に対して
(a+b)+c=a+(b+c)
を示します。そこで c についての数学的帰納法で証明します。
- c=0 の時
(a+b)+0=a+b=a+(b+0) より成り立ちます。
- c=k の時に結合則が成り立つとすると、
(a+b)+k=a+(b+k)
- c=S(k) の時
(a+b)+S(k)=S((a+b)+k)(∵加法の定義)=S(a+(b+k))(∵c=kでの仮定)=a+S(b+k)(∵加法の定義)=a+(b+S(k))(∵加法の定義)
より成り立ちます。よって任意の c∈N について結合則が成り立ちます。
可換性
また数学的帰納法です。
任意の a,b∈N に対して
a+b=b+a
を示します。そこで b についての数学的帰納法で証明します。
- b=0 の時
a+0=a=0+a より成り立ちます。最後の等式は後の補題1で示します。
- b=k の時に可換則が成り立つとすると、
a+k=k+a
- b=S(k) の時
a+S(k)=S(a+k)(∵加法の定義)=S(k+a)(∵b=kでの仮定)=S(k)+a(∵後の補題2)
より成り立ちます。よって任意の b∈N について可換則が成り立ちます。
補題1
任意の a∈N について
0+a=a
を示します。 a についての数学的帰納法です。
- a=0 の時
0+0=0 より成り立ちます。
- a=k の時に成り立つとすると、
0+k=k
- a=S(k) の時
0+S(k)=S(0+k)(∵加法の定義)=S(k)(∵a=kでの仮定)
より成り立ちます。よって任意の a∈N について 0+a=a が成り立ちます。
補題2
任意の n,m∈N について
S(n)+m=S(n+m)
を示します。 m についての数学的帰納法です。
m についての数学的帰納法で証明します。
- m=0 の時
S(n)+0=S(n)=S(n+0) より成り立ちます。
- m=k の時に成り立つとすると、
S(n)+k=S(n+k)
- m=S(k) の時
S(n)+S(k)=S(S(n)+k)(∵加法の定義)=S(S(n+k))(∵m=kでの仮定)=S(n+S(k))(∵加法の定義)
より成り立ちます。よって任意の m∈N について S(n)+m=S(n+m) が成り立ちます。
乗法
同様に乗法は有理数を構成するのに使います。
これも再帰的に定義します。つまり、 n,m∈N に対して、
n⋅0=0n⋅S(m)=n⋅m+n
と n⋅(mの次) を n⋅m+nとして定義します。すると、
n⋅0=0n⋅1=n⋅S(0)=n⋅0+n=0+n=nn⋅2=n⋅S(1)=n⋅1+n=n+nn⋅3=n⋅S(2)=n⋅2+n=(n+n)+n⋮
のように我々の知る自然数の積として機能します。そして積も結合性、可換性が成り立ちます。また分配則も成り立ちます。半環ですね。
結合性・可換性・分配則の証明
分配則
結合性を示すには分配則が必要なので先に分配則を示します。
任意の a,b,c∈N について
a⋅(b+c)=a⋅b+a⋅c
が成り立つことを c に関する数学的帰納法で示します。
- c=0 の時
a⋅(b+0)=a⋅b=a⋅b+0=a⋅b+a⋅0 より成り立ちます。
- c=k の時に分配則が成り立つとすると、
a⋅(b+k)=a⋅b+a⋅k
- c=S(k) の時
a⋅(b+S(k))=a⋅S(b+k)(∵加法の定義)=a⋅(b+k)+a(∵乗法の定義)=(a⋅b+a⋅k)+a(∵c=kでの仮定)=a⋅b+(a⋅k+a)(∵加法の結合性)=a⋅b+a⋅S(k)(∵乗法の定義)
より成り立ちます。よって任意の c∈N について分配則が成り立ちます。
結合性
任意の a,b,c∈N について
(a⋅b)⋅c=a⋅(b⋅c)
が成り立つことを c に関する数学的帰納法で示します。
- c=0 の時
(a⋅b)⋅0=0=a⋅0=a⋅(b⋅0) より成り立ちます。
- c=k の時に成り立つとすると、
(a⋅b)⋅k=a⋅(b⋅k)
- c=S(k) の時
(a⋅b)⋅S(k)=(a⋅b)⋅k+a⋅b(∵乗法の定義)=a⋅(b⋅k)+a⋅b(∵c=kでの仮定)=a⋅(b⋅k+b)(∵分配則)=a⋅(b⋅S(k))(∵乗法の定義)
より成り立ちます。よって任意の c∈N について結合則が成り立ちます。
可換性
任意の a,b∈N について
a⋅b=b⋅a
が成り立つことを b に関する数学的帰納法で示します。
- b=0 の時
a⋅0=0=0⋅a より成り立ちます。最後の等式は後の補題3で示します。
- b=k の時に成り立つとすると、
a⋅k=k⋅a
- c=S(k) の時
a⋅S(k)=a⋅k+a(∵乗法の定義)=k⋅a+a(∵c=kでの仮定)=S(k)⋅a(∵後の補題4)
より成り立ちます。よって任意の b∈N について可換則が成り立ちます。
補題3
任意の a∈N について
0⋅a=0
を示します。 a についての数学的帰納法です。
- a=0 の時
0⋅0=0 より成り立ちます。
- a=k の時に成り立つとすると、
0⋅k=0
- a=S(k) の時
0⋅S(k)=0⋅k+0(∵乗法の定義)=0+0(∵a=kでの仮定)=0
より成り立ちます。よって任意の a∈N について成り立ちます。
補題4
任意の n,m∈N について
S(n)⋅m=n⋅m+m
を示します。 m についての数学的帰納法です。
- m=0 の時
S(n)⋅0=0=0+0=n⋅0+0 より成り立ちます。
- m=k の時に成り立つとすると、
S(n)⋅k=n⋅k+k
- m=S(k) の時
S(n)⋅S(k)=S(n)⋅k+S(n)(∵乗法の定義)=(n⋅k+k)+S(n)(∵m=kでの仮定)=S((n⋅k+k)+n)(∵加法の定義)=S(n⋅k+(k+n))(∵加法の結合性)=n⋅k+S(k+n)(∵加法の定義)=n⋅k+S(n+k)(∵加法の可換性)=n⋅k+(n+S(k))(∵加法の定義)=(n⋅k+n)+S(k)(∵加法の結合性)=n⋅S(k)+S(k)(∵乗法の定義)
より成り立ちます。よって任意の m∈N について成り立ちます。
順序
順序は有理数の完備化で使います。
これは単に、 n,m∈N に対して
n+k=m となる k∈N が存在する時 n≤m と定義します。つまり、(まだ定義していませんが) m−n が自然数なら n≤m です。
これは反射律、反対称律、推移律、全順序律を満たす全順序です。全順序自体我々が普段考える「数」つまり自然数、整数、有理数、実数で成り立つ性質が一般化されたものなのである意味当然ですね。
全順序であることの証明
証明
・反射律
任意の n∈N について n+0=n より n≤n
・反対称律
任意のn,m∈N について n≤m かつ m≤n なら n+k1=m,m+k2=n となる k1,k2∈N が存在します。すると結合則より
m+(k1+k2)=m となるので後の補題5より k1+k2=0 、補題6より k1=k2=0 よって n=n+0=m
・推移律
任意の n,l,m∈N について n≤l かつ l≤m なら n+k1=l,l+k2=m となる k1,k2∈N が存在し、 n+(k1+k2)=m よって n≤m
・全順序律
任意の n,m∈N について n≤m または m≤n が成り立つことを n,m に関する数学的帰納法で示します。
n に関して、
- n=0 の時
0+m=m より 0≤m で成り立ちます。
- n=k の時に成り立つとすると
k≤m または m≤k
- n=S(k) の時
m に関して、
3.1. m=0 の時
0+S(k)=S(k) より 0≤S(k) で成り立ちます。
3.2 m=l の時に成り立つとすると
k≤l または l≤k
3.3 m=S(l) の時
・ k≤l なら t∈N で k+t=l と表すと S(k)+t=S(k+t)=S(l) で S(k)≤S(l)
・ l≤k なら t∈N で l+t=k と表すと S(l)+t=S(l+t)=S(k) で S(l)≤S(k)
よって任意の n,m∈N について成り立ちます。
以上が成り立つのでこれは全順序です。
補題5
m+t=m なら t=0 となることを m に関する数学的帰納法で示します。
- m=0 の時
t=0+t=0 より成り立ちます。
- m=k の時に成り立つとすると
k+t=k⇒t=0
- m=S(k) の時
S(k+t)=S(k)+t=S(k)
ならペアノの公理の4つ目の命題( S は単射)より k+t=k で、 m=k での仮定より t=0 です。
補題6
a,b∈N について
a+b=0 なら a=b=0
となることを b に関する数学的帰納法で示します。
- b=0 の時、
a=a+0=0 より a=0 で成り立ちます。
- b=k の時に成り立つとして、
- b=S(k) の時
ペアノの公理の3つ目の命題(S で 0 にうつることはない)より S(a+k)=a+S(k)=0 にはなり得ません。前提が偽なので成り立ちます。
よって任意の b∈N について a+b=0 なら a=0 です。よって b=0+b=0 で、 a=b=0 となります。
よって任意の m∈N について成り立ちます。
整数の構成
同値関係による構成
整数と自然数の決定的な違いは減法について閉じているかどうかです。 n,m∈N に対して n−m は自然数の中に存在するとは限らないため、そこで n−m を組 (n,m) そのものとして捉えてしまいます。しかしこれでは、同じ結果になる引き算の組で違う元を表すことになってしまうため、ここに同値関係を入れます。つまり、 a−b=c−d⇔a+d=b+c となる時に同値関係 (a,b)∼(c,d) が成り立つとします。 N×N のこの同値関係による商集合を整数 Z とします。
同値関係による商集合というのは、集合 X に同値関係 ∼ が定義されているとき、 x∈X に対して a∼x となる a∈X 全体の集合を1つ1つの元として持つ集合のことで、 X/∼ と表します。その元であるそれぞれの集合のことを同値類と言い、 [x] と書きます。
ここでは整数を Z:=N×N/∼ と定義します。
我々の普段使う書き方と合わせると、 n∈N に対して n:=[(n,0)],−n:=[(0,n)]∈Z となります。
同値関係であることの証明
証明
N×N に
(a,b)∼(c,d)⇔a+d=b+c
という関係を入れると同値関係となります。
・反射律
(a,b)∈N×N について
a+b=b+a より (a,b)∼(a,b)
・対称律
(a,b),(c,d)∈N×N について
(a,b)∼(c,d) なら
a+d=b+c より c+b=d+a
よって (c,d)∼(a,b)
・推移律
(a,b),(c,d),(e,f)∈N×N について
(a,b)∼(c,d),(c,d)∼(e,f) なら
a+d=b+c,c+f=d+e
よって (a+d)+(c+f)=(b+c)+(d+e)
自然数の加法の結合性・可換性より (a+f)+(c+d)=(b+e)+(c+d)
後の補題7より a+f=b+e
よって (a,b)∼(e,f)
補題7
a,b,c∈N について
a+c=b+c⇒a=b
を c についての数学的帰納法で示します。(逆は自明)
- c=0 の時
加法の定義より a+0=b+0⇔a=b で成り立ちます。
- c=k の時に成り立つとすると、
a+k=b+k⇒a=b
- c=S(k) の時
a+S(k)=b+S(k) なら加法の定義より S(a+k)=S(b+k)
ペアノの公理の4つ目の命題(後者関数 S は単射)より a+k=b+k
よって c=k での仮定より a=b
より成り立ちます。よって任意の c∈N について a+c=b+c⇒a=b が成り立ちます。
加法・減法
自然数での加法から整数での加法・減法を定めます。
我々の知る四則演算では (a−b)+(c−d)=(a+c)−(b+d) となるので、
[(a,b)],[(c,d)]∈Z に対して
[(a,b)]+[(c,d)]:=[(a+c,b+d)] と定めるとこれはwell-definedで、結合性、可換性が成り立ちます。
−(c−d)=d−c を考えると −[(c,d)]=[(d,c)] となっていて欲しいです。なので減法を加法の逆演算として定めると
[(a,b)]−[(c,d)]:=[(a,b)]+[(d,c)]=[(a+d,b+c)] となります。加法がwell-definedなのでこれも当然well-definedです。結合性、可換性は成り立たないので注意です。
well-defined性、結合性・可換性の証明
well-defined性
自然数の加法の結合性・可換性より、 a,b,c∈N とすると
(a+c,b+c)∼(a,b)(∵(a+c)+b=(b+c)+a)
これを使うと、 [(a,b)],[(a′,b′)],[(c,d)],[(c′,d)]∈Z として
(a,b)∼(a′,b′),(c,d)∼(c′,d′) の時、 a+b′=a′+b,c+d′=c′+d より
[(a′,b′)]+[(c′,d′)]:=[(a′+c′,b′+d′)]=[(a′+c′+(b+d),b′+d′+(b+d))]=[(a+c+(b′+d′),b+d+(b′+d′))](∵結合性・可換性)=[(a+c,b+d)]
となるので整数の加法は代表元の取り方によりません。減法も対称性によりwell-definedです。
結合性
整数の加法の結合性は自然数の加法の結合性から即座に従い、
[(a,b)],[(c,d)],[(e,f)]∈Z について
([(a,b)]+[(c,d)])+[(e,f)]=[(a+c,b+d)]+[(e,f)]=[((a+c)+e,(b+d)+f)]=[(a+(c+e),b+(d+f))]=[(a,b)]+([(c,d)]+[(e,f)])
となります。
可換性
加法の可換性も自然数の加法の可換性からすぐに従い、
[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)]=[(c+a,d+b)]=[(c,d)]+[(a,b)]
となります。
乗法
同じく自然数での乗法から整数での乗法を定めます。
これも我々の知る演算では (a−b)⋅(c−d)=(a⋅c+b⋅d)−(a⋅d+b⋅c) となるので、
[(a,b)],[(c,d)]∈Z に対して
[(a,b)]⋅[(c,d)]:=[(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)] と定めるとこれはwell-definedとなり、結合性、可換性が成り立ちます。やはり分配則も成り立ちます。今度は加法の逆元 −[(a,b)]=[(b,a)] が入って可換環になりました。
well-defined性、結合性・可換性・分配則の証明
well-defined性
[(a,b)],[(a′,b′)],[(c,d)],[(c′,d′)]∈Z として
(a,b)∼(a′,b′),(c,d)∼(c′,d′) の時、
[(a′⋅c′+b′⋅d′,a′⋅d′+b′⋅c′)]=[(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)]
を示す必要があります。
a+b′=a′+b,c+d′=c′+d が成り立ち、この両辺に c,d,a′,b′ をかけて分配則より
⎩⎨⎧a′⋅c+b⋅c=a⋅c+b′⋅ca⋅d+b′⋅d=a′⋅d+b⋅da′⋅c′+a′⋅d=a′⋅c+a′⋅d′b′⋅c+b′⋅d′=b′⋅c′+b′⋅d
の4式を得ます。
左辺と右辺同士で足し合わせると
(a′⋅c+b⋅c)+(a⋅d+b′⋅d′)+(a′⋅c′+a′⋅d)+(b′⋅c+b′⋅d′)=(a⋅c+b′⋅c)+(a′⋅d+b⋅d)+(a′⋅c+a′⋅d′)+(b′⋅c′+b′⋅d)
となり、加法の可換性・結合性及び補題7を用いて整理すると
(a′⋅c′+b′⋅d′)+(a⋅d+b⋅c)=(a′⋅d′+b′⋅c′)+(a⋅c+b⋅d)
となるので
(a′⋅c′+b′⋅d′,a′⋅d′+b′⋅c′)∼(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)
で、
[(a′,b′)]⋅[(c′,d′)]=[(a,b)]⋅[(c,d)]
となり整数の乗法は代表元の取り方によりません。
結合性
[(a,b)],[(c,d)],[(e,f)]∈Z について
自然数についての結合性・可換性・分配則より
([(a,b)]⋅[(c,d)])⋅[(e,f)]=[(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)]⋅[(e,f)]=[((a⋅c+b⋅d)⋅e+(a⋅d+b⋅c)⋅f,(a⋅c+b⋅d)⋅f+(a⋅d+b⋅c)⋅e)]=[(((a⋅c)⋅e+(b⋅d)⋅e)+((a⋅d)⋅f+(b⋅c)⋅f),((a⋅c)⋅f+(b⋅d)⋅f)+((a⋅d)⋅e+(b⋅c)⋅e)))]
[(a,b)]⋅([(c,d)]⋅[(e,f)])=[(a,b)]⋅[(c⋅e+d⋅f,c⋅f+d⋅e)]=[(a⋅(c⋅e+d⋅f)+b⋅(c⋅f+d⋅e),a⋅(c⋅f+d⋅e)+b⋅(c⋅e+d⋅f))]=[((a⋅(c⋅e)+a⋅(d⋅f))+(b⋅(c⋅f)+b⋅(d⋅e)),(a⋅(c⋅f)+a⋅(d⋅e))+(b⋅(c⋅e)+b⋅(d⋅f)))]
となります。また結合性・可換性から
((a⋅c)⋅e+(b⋅d)⋅e)+((a⋅d)⋅f+(b⋅c)⋅f)+(a⋅(c⋅f)+a⋅(d⋅e))+(b⋅(c⋅e)+b⋅(d⋅f))=((a⋅c)⋅f+(b⋅d)⋅f)+((a⋅d)⋅e+(b⋅c)⋅e))+(a⋅(c⋅e)+a⋅(d⋅f))+(b⋅(c⋅f)+b⋅(d⋅e))
となるのでこれらは等しく、 ([(a,b)]⋅[(c,d)])⋅[(e,f)]=[(a,b)]⋅([(c,d)]⋅[(e,f)]) です。すなわち乗法の結合性が成り立ちます。
可換性
[(a,b)],[(c,d)]∈Z について
[(a,b)]⋅[(c,d)]=[(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)][(c,d)]⋅[(a,b)]=[(c⋅a+d⋅b,c⋅b+d⋅a)]
であり、自然数についての可換性よりこれらは等しいため [(a,b)]⋅[(c,d)]=[(c,d)]⋅[(a,b)] です。すなわち乗法の可換性が成り立ちます。
分配則
[(a,b)],[(c,d)],[(e,f)]∈Z について
自然数についての結合性・可換性・分配則より
[(a,b)]⋅([(c,d)]+[(e,f)])=[(a,b)]⋅[(c+e,d+f)]=[(a⋅(c+e)+b⋅(d+f),a⋅(d+f)+b⋅(c+e))]=[((a⋅c+a⋅e)+(b⋅d+b⋅f),(a⋅d+a⋅f)+(b⋅c+b⋅e))]=[((a⋅c+b⋅d)+(a⋅e+b⋅f),(a⋅d+b⋅c)+(a⋅f+b⋅e))]=[(a⋅c+b⋅d,a⋅d+b⋅c)]+[(a⋅e+b⋅f,b⋅c+b⋅e)]=[(a,b)]⋅[(c,d)]+[(a,b)]⋅[(e,f)]
となります。すなわち分配則が成り立ちます。
順序
これもまた自然数の順序から整数の順序を定めます。
同じように考えると (a−b)≤(c−d)⇔a+d≤b+c なので、
[(a,b)],[(c,d)]∈Z に対して
[(a,b)]≤[(c,d)]defa+d≤b+c と定めるとこれはwell-definedとなり、全順序です。また自然数の順序自体加法から定められたものなのでこの順序は環構造と両立して順序環になります。
well-defined性、全順序であることの証明
well-defined性
[(a,b)],[(a′,b′)],[(c,d)],[(c′,d′)]∈Z として
(a,b)∼(a′,b′),(c,d)∼(c′,d′) の時、
a′+d′≤b′+c′⇔a+d≤b+c
となることを示したいです。
ここで補題7より、 a,b,c∈N として
a≤b⇔∃k∈N s.t. a+k=b⇔∃k∈N s.t. (a+k)+c=b+c⇔a+c≤b+c
となることを使うと、 a+b′=a′+b,c+d′=c′+d より
[(a′,b′)]≤[(c′,d′)]⇔a′+d′≤b′+c′⇔(a′+d′)+(b+c)≤(b′+c′)+(b+c)⇔(a+b′)+(c′+d)≤(b′+c′)+(b+c)⇔a+d≤b+c⇔[(a,b)]≤[(c,d)]
となり、順序は代表元の取り方によりません。
全順序
・反射律
任意の [(a,b)]∈Z について、
a+b≤b+a より [(a,b)]≤[(a,b)]
・反対称律
任意の [(a,b)],[(c,d)]∈Z について [(a,b)]≤[(c,d)] かつ [(c,d)]≤[(a,b)] なら a+d≤b+c かつ b+c≤a+d より a+d=b+c となります。よって (a,b)∼(c,d) で [(a,b)]=[(c,d)]
・推移律
任意の [(a,b)],[(c,d)],[(e,f)]∈Z について [(a,b)]≤[(c,d)] かつ [(c,d)]≤[(e,f)] なら a+d≤b+c かつ c+f≤e+d となります。よって (a+d)+f≤(b+c)+f,b+(c+f)≤b+(e+d) より (a+d)+f≤b+(e+d) で、a+f≤b+e で、 [(a,b)]≤[(e,f)]
・全順序律
任意の [(a,b)],[(c,d)]∈Z について、
a+d≤b+c または b+c≤a+d 、すなわち [(a,b)]≤[(c,d)] または [(c,d)]≤[(a,b)] が成り立ちます。
以上が成り立つのでこれは全順序です。
有理数の構成
r1,r2∈Z,s1,s2∈S:=Z\{0} として
s1r1=s2r2⇔s1⋅s2r1⋅s2−r2⋅s1=0
の時に等しくなるようにしたいため、
Z×S に次のような同値関係を入れます。
(r1,s1)∼(r2,s2)⇔∃t∈S s.t. t⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0
はい。実はこの場合は t なんて入れなくても同値関係になるんですが、 整数環が整域であることを示すのが面倒なのでこれは環の局所化という操作の具体的な場合で、環 Z の積閉集合 S による局所化なので t をかけています。
それで有理数を Q:=Z×S/∼ と定めます。環の局所化として書くなら S−1Z となります。
我々の普段の書き方では sr:=[(r,s)] となります。こっちは割と直感的ですね。
同値関係について
同値関係
実は
Z×S に
(r1,s1)∼(r2,s2)⇔r1⋅s2−r2⋅s1=0
という関係を入れるとこれは同値関係になります。
- 反射律
(r,s)∈Z×S について r⋅s−r⋅s=0 より (r,s)∼(r,s)
- 対称律
(r1,s1),(r2,s2)∈Z×S について
(r1,s1)∼(r2,s2) なら
r1⋅s2−r2⋅s1=0 より r2⋅s1−r1⋅s2=0
よって (r2,s2)∼(r1,s1)
- 推移律
(r1,s1),(r2,s2),(r3,s3)∈Z×S について
(r1,s1)∼(r2,s2),(r2,s2)∼(r3,s3) なら
r1⋅s2−r2⋅s1=0,r2⋅s3−r3⋅s2=0
よって s3⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0,s1⋅(r2⋅s3−r3⋅s2)=0
足して s2⋅(s1⋅r3−s3⋅r1)=0
(前に示した結合性・可換性、分配則を使っています。)
ここで s2∈S=Z\{0} は 0 ではなく、 Z は整域なので s1⋅r3−s3⋅r1=0 で (r1,s3)∼(r3,s1) となるんですが、整数環が整域であることをペアノの公理から示すのが面倒なので、
同値関係を
(r1,s1)∼(r2,s2)⇔∃t∈S s.t. t⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0
と定めます。
すると、
- 反射律
(r,s)∈Z×S について t⋅(r⋅s−r⋅s)=0 より (r,s)∼(r,s)
- 対称律
(r1,s1),(r2,s2)∈Z×S について
(r1,s1)∼(r2,s2) なら
t⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0 より t⋅(r2⋅s1−r1⋅s2)=0
よって (r2,s2)∼(r1,s1)
- 推移律
(r1,s1),(r2,s2),(r3,s3)∈Z×S について
(r1,s1)∼(r2,s2),(r2,s2)∼(r3,s3) なら
t1⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0,t2⋅(r2⋅s3−r3⋅s2)=0
よって s3⋅t2⋅t1⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0,s1⋅t1⋅t2⋅(r2⋅s3−r3⋅s2)=0
足して t1⋅t2⋅s2⋅(s1⋅r3−s3⋅r1)=0
よって (r1,s3)∼(r3,s1)
以上が成り立つのでこれは同値関係です。
加法・減法
整数の加減法・乗法から有理数での加法・減法を定めます。
s1r1,s2r2∈Q に対して
s1r1+s2r2=s1⋅s2r1⋅s2+r2⋅s1
となって欲しいので
[(r1,s1)],[(r2,s2)]∈Q に対して
[(r1,s1)]+[(r2,s2)]=[(r1⋅s2+r2⋅s1,s1⋅s2)]
と定めます。これはwell-definedで、結合性、可換性が成り立ちます。
また [(r2,s2)] を −[(r2,s2)]=[(−r2,s2)] に置き換えると、減法は
[(r1,s1)]−[(r2,s2)]=[(r1⋅s2−r2⋅s1,s1⋅s2)]
となります。加法の逆演算なのでやはりwell-definedで、結合性、可換性は成り立ちません。
well-defined性、結合性・可換性の証明
well-defined性
[(r1,s1)],[(r1′,s1′)],[(r2,s2)],[(r2′,s2′)]∈Q として
(r1,s1)∼(r1′,s1′),(r2,s2)∼(r2′,s2′) の時、 t1⋅(r1⋅s1′−r1′⋅s1)=0,t2⋅(r2⋅s2′−r2′⋅s2)=0 となる t1,t2∈S が存在します。
[(r1,s1)]+[(r2,s2)]:=[(r1⋅s2+r2⋅s1,s1⋅s2)][(r1′,s1′)]+[(r2′,s2′)]:=[(r1′⋅s2′+r2′⋅s1′,s1′⋅s2′)]
で
(r1⋅s2+r2⋅s1)⋅(s1′⋅s2′)−(r1′⋅s2′+r2′⋅s1′)⋅(s1⋅s2)=(r1⋅s1′−r1′⋅s1)⋅(s2⋅s2′)−(r2⋅s2′−r2′⋅s2)⋅(s1⋅s1′)
なので t1⋅t2 をかけて
((t1⋅t2)⋅(s1′⋅s2′))((r1⋅s2+r2⋅s1)⋅(s1′⋅s2′)−(r1′⋅s2′+r2′⋅s1′)⋅(s1⋅s2))=(t1⋅(r1⋅s1′−r1′⋅s1))⋅(t2⋅(s2⋅s2′))−(t2⋅(r2⋅s2′−r2′⋅s2))⋅(t1⋅(s1⋅s1′))=0⋅(t2⋅(s2⋅s2′))−0⋅(t1⋅(s1⋅s1′))=0−0=0
となります。よって有理数の加法は代表元の取り方によりません。ただし、 [(a,b)]∈Z について 0⋅[(a,b)]=[(0⋅a+0⋅b,0⋅b+0⋅a)]=0,0−0=[(0+0,0+0)]=0 を用いました。またこれにより減法もwell-definedです。
結合性
[(r1,s1)],[(r2,s2)],[(r3,s3)]∈Q について
([(r1,s1)]+[(r2,s2)])+[(r3,s3)]=[(r1⋅s2+r2⋅s1,s1⋅s2)]+[(r3,s3)]=[((r1⋅s2+r2⋅s1)⋅s3+r3⋅(s1⋅s2),(s1⋅s2)⋅s3)]
[(r1,s1)]+([(r2,s2)]+[(r3,s3)])=[(r1,s1)]+[(r2⋅s3+r3⋅s2,s2⋅s3)]=[(r1⋅(s2⋅s3)+(r2⋅s3+r3⋅s2)⋅s1,s1⋅(s2⋅s3))]
整数についての結合性・可換性によりこれらは一致します。すなわち加法の結合性が成り立ちます。
可換性
[(r1,s1)],[(r2,s2)]∈Q について
[(r1,s1)]+[(r2,s2)]=[(r1⋅s2+r2⋅s1,s1⋅s2)][(r2,s2)]+[(r1,s1)]=[(r2⋅s1+r1⋅s2,s2⋅s1)]
で整数についての可換性よりこれらは一致します。すなわち加法の可換性が成り立ちます。
乗法・除法
同じく整数の乗法から有理数での乗法・除法を定めます。
s1r1,s2r2∈Q に対して
s1r1⋅s2r2=s1⋅s2r1⋅r2
となって欲しいので
[(r1,s1)]⋅[(r2,s2)]=[(r1⋅r2,s1⋅s2)]
と定めます。これはwell-definedとなり、結合性、可換性が成り立ちます。分配則も成り立ちます。有理数自体掛け算・割り算がモチベーションとして作られているため定義が単純ですね。
除法は r2=0 、つまり [(r2,s2)] が乗法に関して逆元を持つ時に定められ、 [(r2,s2)] を [(s2,r2)] に置き換えて、
[(r1,s1)]÷[(r2,s2)]=[(r1⋅s2,s1⋅r2)]
となります。well-definedで、結合性、可換性は成り立ちません。
well-defined性、結合性・可換性、分配則の証明
well-defined性
[(r1,s1)],[(r1′,s1′)],[(r2,s2)],[(r2′,s2′)]∈Q として
(r1,s1)∼(r1′,s1′),(r2,s2)∼(r2′,s2′) の時、 t1⋅(r1⋅s1′−r1′⋅s1)=0,t2⋅(r2⋅s2′−r2′⋅s2)=0 となる t1,t2∈S が存在します。
[(r1,s1)]⋅[(r2,s2)]:=[(r1⋅r2,s1⋅s2)][(r1′,s1′)]⋅[(r2′,s2′)]:=[(r1′⋅r2′,s1′⋅s2′)]
で
(r1⋅r2)⋅(s1′⋅s2′)−(r1′⋅r2′)⋅(s1⋅s2)=(r1⋅s1′−r1′⋅s1)⋅(r2⋅s2′)+(r2⋅s2′−r2′⋅s2)⋅(r1′⋅s1)
なので t1,t2 をかけて
(t1⋅t2)⋅((r1⋅r2)⋅(s1′⋅s2′)−(r1′⋅r2′)⋅(s1⋅s2))=(t1⋅(r1⋅s1′−r1′⋅s1))⋅(t2⋅(r2⋅s2′))+(t2⋅(r2⋅s2′−r2′⋅s2))⋅(t1⋅(r1′⋅s1))=0⋅(t2⋅(r2⋅s2′))+0⋅(t1⋅(r1′⋅s1))=0+0=0
となります。よって有理数の乗法は代表元の取り方によりません。またこれにより除法もwell-definedです。
結合性
乗法の結合性は整数の乗法の結合性から直ちに従い、
[(r1,s1)],[(r2,s2)],[(r3,s3)]∈Q について
([(r1,s1)]⋅[(r2,s2)])⋅[(r3,s3)]=[(r1⋅r2,s1⋅s2)]⋅[(r3,s3)]=[((r1⋅r2)⋅r3,(s1⋅s2)⋅s3)]=[(r1⋅(r2⋅r3),s1⋅(s2⋅s3))]=[(r1,s1)]⋅([(r2,s2)]⋅[(r3,s3)])
となります。
可換性
可換性も整数の乗法の可換性からすぐに従い、
[(r1,s1)],[(r2,s2)]∈Q について
[(r1,s1)]⋅[(r2,s2)]=[(r1⋅r2,s1⋅s2)]=[(r2⋅r1,s2⋅s1)]=[(r2,s2)]⋅[(r1,s1)]
となります。
分配則
[(r1,s1)],[(r2,s2)],[(r3,s3)]∈Q について
[(r1,s1)]⋅([(r2,s2)]+[(r3,s3)])=[(r1,s1)]⋅[(r2⋅s3+r3⋅s2,s2⋅s3)]=[(r1⋅(r2⋅s3+r3⋅s2),s1⋅(s2⋅s3))]=[(r1⋅(r2⋅s3)+r1⋅(r3⋅s2),s1⋅(s2⋅s3))]
[(r1,s1)]⋅[(r2,s2)]+[(r1,s1)]⋅[(r3,s3)]=[(r1⋅r2,s1⋅s2)]+[(r1⋅r3,s1⋅s3)]=[((r1⋅r2)⋅(s1⋅s3)+(r1⋅r3)⋅(s1⋅s2),(s1⋅s2)⋅(s1⋅s3))]
となります。ここで、 [(r,s)]∈Q,s′∈S について、任意の t∈S で t⋅(r⋅(s⋅s′)−(r⋅s′)⋅s)=t⋅0=0 となるため [(r,s)]=[(r⋅s′,s⋅s′)] が成り立ちます。よって r=(r1⋅(r2⋅s3)+r1⋅(r3⋅s2),s′=s1 とすると
[(r1,s1)]⋅([(r2,s2)]+[(r3,s3)])=[(r1,s1)]⋅[(r2,s2)]+[(r1,s1)]⋅[(r3,s3)]
となります。すなわち分配則が成り立ちます。
順序
s1r1,s2r2∈Q に対して
s1r1≤s2r2⇔s1⋅s2r2⋅s1−r1⋅s2≥0⇔s1⋅s2⋅(r2⋅s1−r1⋅s2)≥0⇔s1⋅s2⋅r1⋅s2≤s1⋅s2⋅r2⋅s1
となって欲しいので、
[(r1,s1)]≤[(r2,s2)]defs1⋅s2⋅r1⋅s2≤s1⋅s2⋅r2⋅s1
と定めるとwell-definedで、全順序です。
well-defined性、全順序であることの証明
well-defined性
[(r1,s1)],[(r1′,s1′)],[(r2,s2)],[(r2′,s2′)]∈Q について、 (r1,s1)∼(r1′,s1′),(r2,s2)∼(r2′,s2′) の時、 t1⋅(r1⋅s1′−r1′⋅s1)=0,t2⋅(r2⋅s2′−r2′⋅s2)=0 となる t1,t2∈S が存在し、すなわち t1⋅r1⋅s1′=t1⋅r1′⋅s1,t2⋅r2⋅s2′=t2⋅r2′⋅s2 となるのでこれを用いると
s1⋅s2⋅(r2⋅s1−r1⋅s2)⋅t1⋅t2⋅s1′⋅s2′⋅s1′⋅s2′=s1′⋅s2′⋅(r2′⋅s1′−r1′⋅s2′)⋅t1⋅t2⋅s1⋅s2⋅s1⋅s2
より
s1⋅s2⋅(r2⋅s1−r1⋅s2)⋅s1′⋅s2′⋅s1′⋅s2′=s1′⋅s2′⋅(r2′⋅s1′−r1′⋅s2′)⋅s1⋅s2⋅s1⋅s2
となり、 0 でない値の2乗は正なので
s1⋅s2⋅(r2⋅s1−r1⋅s2)≥0⇔s1′⋅s2′⋅(r2′⋅s1′−r1′⋅s2′)≥0
となり、順序は代表元の取り方によりません。
全順序
・反射律
任意の [(r,s)]∈Q について、
s⋅s⋅r⋅s≤s⋅s⋅r⋅s より [(r,s)]≤[(r,s)]
・反対称律
任意の [(r1,s1)],[(r2,s2)]∈Q について、
[(r1,s1)]≤[(r2,s2)] かつ [(r2,s2)]≤[(r1,s1)] なら s1⋅s2⋅r1⋅s2≤s1⋅s2⋅r2⋅s1 かつ s1⋅s2⋅r2⋅s1≤s1⋅s2⋅r1⋅s2 より s1⋅s2⋅r1⋅s2=s1⋅s2⋅r2⋅s1
よって s1⋅s2⋅(r1⋅s2−r2⋅s1)=0 より [(r1,s1)]=[(r2,s2)]
・推移律
任意の [(r1,s1)],[(r2,s2)],[(r3,s3)]∈Q について、
[(r1,s1)]≤[(r2,s2)] かつ [(r2,s2)]≤[(r3,s3)] なら s1⋅s2⋅r1⋅s2≤s1⋅s2⋅r2⋅s1 かつ s2⋅s3⋅r2⋅s3≤s2⋅s3⋅r3⋅s2 となります。両辺にそれぞれ正の数 s32,s12 をかけると
s1⋅s2⋅r1⋅s2⋅s3⋅s3≤s1⋅s2⋅r2⋅s1⋅s3⋅s3≤s2⋅s3⋅r3⋅s2⋅s1⋅s1
s2⋅s2 は正なので s1⋅s3⋅r1⋅s3≤s1⋅s3⋅r3⋅s1 を得ます。
・全順序律
任意の [(r1,s1)],[(r2,s2)]∈Q について、
s1⋅s2⋅r1⋅s2≤s1⋅s2⋅r2⋅s1 または s1⋅s2⋅r2⋅s1≤s1⋅s2⋅r1⋅s2 、すなわち [(r1,s1)]≤[(r2,s2)] または [(r2,s2)]≤[(r1,s1)] が成り立ちます。
以上が成り立つのでこれは全順序です。
実数の構成
やっと実数です。別にデデキント切断で定義しても上限性質で定義しても同値なんですが、初等的な分野で実数での議論をしたい時というのは大抵数列や関数の極限を考える時で、最初からコーシー列で定義した方が議論がしやすいと思います。なのでこの記事ではコーシー列の収束で実数を構成します。
皆さんご存じのように数列が収束することとその数列がコーシー列であることは同値です。一応確認しておくと、実数列 {xn} が x に収束するというのは、任意の ϵ∈R>0 に対してある N∈N が存在して n≥N では ∣xn−x∣<ϵ となる、つまり数列の値がある値にいくらでも近づいていくことができるということです。またコーシー列というのは任意の ϵ∈R>0 に対してある N∈N が存在して n,m≥N では ∣xn−xm∣<ϵ となる、つまり数列の値の差をいくらでも小さくすることができるということです。これが同値なわけですが、これを有理数で考えてみます。
例えば有理数の数列
{x0=2xn+1=21xn+2xn3
はニュートン法より 3 に収束します。
ですが 3 は無理数であり、これは有理数のコーシー列ではありますが、有理数の範囲で収束先を持ちません。そこで、この数列そのものを「数」として見ることにします。極限の線形性よりこの数列のそれぞれの項に対する四則演算は収束先での演算と見なすことができるため、これは数とみなすことができます。ですがこれでは同じ「数」を表すのに複数の数列が対応してしまいますから、ここで同値関係を考えます。
数列 {xn},{yn} が同じ値 a に収束するとします。すると任意の ϵ(>0) について N,M∈N が存在して n≥N の時 ∣xn−a∣<2ϵ、m≥M の時 ∣ym−a∣<2ϵ であり、 K=max{N,M} とすると、 n,m≥K の時三角不等式より ∣xn−ym∣<ϵ となります。
逆に、 {xn} が a に収束し、 任意の ϵ(>0) について K∈N が存在して m≥K の時 ∣xn−ym∣<ϵ が成り立つとすれば、同様に三角不等式により数列 {yn} は a に収束します。
よって、「収束列 {xn},{ym} の収束先が等しい」 ⇔ 「任意の ϵ(>0) に対してある K∈N が存在して n,m≥K では ∣xn−ym∣<ϵ となる」であることがわかります。
さて、コーシー列に対して収束先の値を使わずに、同じ値に収束するかどうかを確かめたいので、同値関係は後者で定めれば良いでしょう。それでは実数を定義します。
まず、有理数列 {xn} とは自然数の集合 N から有理数の集合 Q の写像 N∋n⟼xn∈Q のことです。また絶対値 ∣⋅∣ は非負の時はそのまま、負の時はその逆符号を表します。そして有理数のコーシー列全体の集合を C とし、 C 上の同値関係を定めます。すなわち、
{xn}∼{ym}def∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣xn−ym∣<ϵ
とします。
これは同値関係となるので、実数を R:=C/∼ と定めます。この操作のことを有理数の(絶対値距離による)完備化と言います。
同値関係であることの証明
証明
C に
{xn}∼{yn}⇔∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣xn−ym∣<ϵ
という関係を入れると同値関係となります。
・反射律
{xn}∈C について
∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣xn−xm∣<ϵ
というのは {xn} がコーシー列であることそのものなので {xn}∼{xn}です。
・対称律
{xn},{yn}∈C について、 ∣xn−ym∣=∣ym−xn∣ より
{xn}∼{yn}⇒∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣xn−ym∣<ϵ⇒∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣ym−xn∣<ϵ⇒∀ϵ∈Q>0 ∃K∈N s.t. n,m≥K⇒∣yn−xm∣<ϵ⇒{yn}∼{xn}
・推移律
{xn},{yn},{zn}∈C について、 {xn}∼{yn},{yn}∼{zn} なら任意の ϵ∈Q>0 についてある K1,K2∈N が存在して n,l≥K1 なら ∣xn−yl∣<2ϵ l,m≥K2 なら ∣yl−zm∣<2ϵ となる。
よって、 K=max{K1,K2} とすれば、 n,m≥K の時、 任意の l≥K を用いて三角不等式より
∣xn−zm∣=∣(xn−yl)+(yl−zm)∣≤∣xn−yl∣+∣yl−zm∣<2ϵ+2ϵ=ϵ
よって {xn}∼{zn}
以上が成り立つのでこれは同値関係です。
有理数上には p 進距離という距離も定義でき、これを使って完備化すると p 進数という数ができます。オストロフスキーの定理という定理から有理数の完備化は本質的に実数と p 進数だけであることがわかるようですが、自分は p 進数には詳しくないので割愛します。
四則演算
数列の極限は線形性が成り立つので数列での四則演算がそのまま使えます。
[{xn}]+[{yn}]:=[{xn+yn}]
[{xn}]−[{yn}]:=[{xn−yn}]
[{xn}]⋅[{yn}]:=[{xn⋅yn}]
と定めるとこれはwell-definedです。
また、[{yn}]=0:=[{0}] の時、ある N∈N が存在して n≥N なら ∣yn∣>0 とすることができるので、この N を用いて
[{xn}]÷[{yn}]:=[{xn÷yn+N}]
とすれば良いです。
well-defined性の証明
加法のwell-defined性
[{xn}],[{xn′}],[{yn}],[{yn′}]∈R として
{xn}∼{xn′},{yn}∼{yn′} の時、
[{xn}]+[{yn}]=[{xn+yn}]
[{xn′}]+[{yn′}]=[{xn′+yn′}]
で
任意の ϵ∈Q>0 についてある K1,K2∈N が存在して n,m≥K1 で ∣xn−xm′∣<2ϵ 、 n,m≥K2 で ∣yn−ym′∣<2ϵ となるので K=max{K1,K2} とすると n,m≥K で三角不等式より
∣(xn+yn)−(xm′+ym′)∣=∣(xn−xm′)+(yn−ym′)∣≤∣xn−xm′∣+∣yn−ym′∣<2ϵ+2ϵ=ϵ
となるので加法は代表元の取り方によりません。そして、 xn′=xn,yn′=yn とすることで {xn+yn} がコーシー列であることも分かります。またこれにより減法もwell-defineddです。
乗法のwell-defined性
[{xn}],[{xn′}],[{yn}],[{yn′}]∈R として
{xn}∼{xn′},{yn}∼{yn′} の時、
[{xn}]⋅[{yn}]=[{xn⋅yn}]
[{xn′}]⋅[{yn′}]=[{xn′⋅yn′}]
で
任意の e∈Q>0 についてある K1,K2∈N が存在して n,m≥K1 で ∣xn−xm′∣<e 、 n,m≥K2 で ∣yn−ym′∣<e となるので K=max{K1,K2} とし、コーシー列は有界(※)なので ∣xn∣ の最大値を xˉ 、 ∣yn∣ の最大値を yˉ とすると n,m≥K で三角不等式より
∣(xn⋅yn)−(xm′⋅ym′)∣=∣(xn−xm′)⋅(yn−ym′)+(xn−xm′)⋅ym′+xm′⋅(yn−ym′)∣≤∣xn−xm′∣⋅∣yn−ym′∣+∣xn−xm′∣⋅∣ym′∣+∣xm′∣⋅∣yn−ym′∣<e2+(xˉ+yˉ)⋅e
となります。(積の絶対値は絶対値の積)なので、任意の ϵ∈Q>0 に対して ϵ>e2+(xˉ+yˉ)⋅e となるように e を取れば、
∣(xn⋅yn)−(xm′⋅ym′)∣<ϵ
となります。よって乗法は代表元の取り方によりません。同様に xn′=xn,yn′=yn とすることで {xn⋅yn} がコーシー列であることも分かります。
ϵ=e2+(xˉ+yˉ)⋅e 、つまり e=ϵ+4(xˉ+yˉ)2−2xˉ+yˉ(>0) となるように ϵ に対して e を取ろうとしても e が有理数になるとは限らないため e をこのように取る必要があります。
(※)ご存知のように、コーシー列 {xn} には a∈Q>0 について N∈N が存在し、 n≥N の時 N≥N より ∣xn−xN∣<a なので、 M=max{∣x1∣,⋯,∣xN∣,∣xN−a∣,∣xN+a∣} とすれば xn≤M となり、コーシー列は有界です。
そのような e が存在する理由
a=xˉ+yˉ とします。
有理数のアルキメデス性は分母分子正の有理数に対して (分母)+1 の自然数を取ることで示せます。具体的には、正の有理数 δ=[(a,b)](b>0) に対して n=b+1 と取ると 0<n1<δ とすることができます。
そのアルキメデス性を用いると、正の有理数
δ:=max{1,2ϵ,2⋅a+1ϵ}
に対して 0<n1<δ となる正の自然数 n を取ることができ、 e=n1 と取ると、
e<1,e<2ϵ より e2<e<2ϵ です。
また、 e<2⋅a+1ϵ より a⋅e<2⋅a+1a⋅ϵ<2ϵ です。
よって e2+(xˉ+yˉ)⋅e<2ϵ+2ϵ=ϵ となります。
除法について
[{yn}]=[{0}] の時、定義の否定よりある ϵ∈Q>0 が存在して任意の N∈N に対して n≥K で ∣yn−0∣≥ϵ となる n∈N が存在します。そのある K に対する n を n0 と表します。
[{yn}] はコーシー列なのである N∈N が存在して n≥N で ∣yn−yn0∣<2ϵ となります。三角不等式より、
∣yn0∣=∣(yn0−yn)+yn∣≤∣yn−yn0∣+∣yn∣
よって
∣yn∣≥∣yn0∣−∣yn−yn0∣>ϵ−2ϵ=2ϵ>0
となります。
また {yn} がコーシー列の時、任意の ϵ∈Q>0 についてある N′ ∈N が存在し、 n,m≥N′ で ∣yn−ym∣<ϵ となるので ϵ に対して max{N′−N,0} を取れば {yn+N} がコーシー列であることがわかります。
順序
[{xn}],[{yn}]∈R について、 [{yn}] が [{xn}] より大きいことを、「十分先の項で差がある正の値より大きくなること」、つまり
[{xn}]<[{yn}]def∃ϵ∈Q>0 ∃N∈N s.t. n≥N⇒xn+ϵ<yn
と定めます。この否定を使って
[{xn}]≤[{yn}]def∀ϵ∈Q>0 ∀N∈N ∃n≥N s.t. xn≤yn+ϵ
と定めるとこれはwell-definedです。
well-defined性の証明
well-defined性
[{xn}],[{xn′}],[{yn}],[{yn′}]∈R として
{xn}∼{xn′},{yn}∼{yn′} の時、
[{xn}]≤[{yn}]
なら、任意の ϵ∈Q>0 について {xn}∼{xn′},{yn}∼{yn′} より N1,N2∈N が存在して n≥N1 なら ∣xn−xn′∣<3ϵ 、 n≥N2 なら ∣yn−yn′∣<3ϵ となります。また、不等式の定義より任意の N∈N について、 n≥max{N1,N2,N} かつ xn≤yn+3ϵ となる n∈N が存在します。
この n について
∣xn−xn′∣<3ϵ より xn′<xn+3ϵ
∣yn−yn′∣<3ϵ より yn<yn′+3ϵ
が成り立つので、
xn′<xn+3ϵ≤(yn+3ϵ)+3ϵ<(yn′+3ϵ)+32⋅ϵ=yn′+ϵ
よって xn′≤yn′+ϵ より [{xn′}]≤[{yn′}] となり、順序は代表元の取り方によりません。
コーシー列の収束
コーシー列の収束先が存在するように実数を定めたので当然実コーシー列はある実数に収束します。そのことは上限性質を導けば通常用いられる証明のようにコーシー列の有界性を使ってボルツァーノ=ワイエルシュトラスの定理により収束部分列の収束先を用いて示せます。しかしこの証明の本質は収束先の候補を指定して実際にその値に収束することを示すことなので、コーシー列で定めた場合、実数列の各項の数列から一つずつ有理数を取ってきて、その列を収束先の候補とするのが自然でしょう。それではその方針で実コーシー列がある実数に収束することを示します。
実コーシー列の定義
実コーシー列の定義は有理数の時と同様、
∀ϵ∈R>0∃N s.t. n,m≥N⇒∣[{xk,n}k∈N]−[{xk,m}k∈N]∣<ϵ
です。ただし、実数の絶対値は代表元の絶対値によって定め、これはwell-definedです。
絶対値のwell-defined性の証明
証明
[{an}]∈R に対して ∣[{an}]∣:=[{∣an∣}] と定めると、
[{an}],[{bn}]∈R として {an}∼{bn} の時、
三角不等式 ∣bm∣≤∣an∣+∣an−bm∣,∣an∣≤∣bm∣+∣an−bm∣ より ∣∣an∣−∣bm∣∣≤∣an−bm∣ が成り立つので
任意の ϵ∈Q>0 についてある N∈N が存在し、 n,m≥N⇒∣an−bm∣<ϵ より
∣∣an∣−∣bm∣∣<ϵ
となり、 絶対値は代表元の取り方によりません。また同様に bn=an とすることで {∣an∣} がコーシー列であることもわかります。
収束先の構成
実コーシー列 {[{ak,n}k∈N]}n∈N を考えます。つまり、 ak,n が実数列の第 n 項の代表元の第 k 項を表すとします。
すると、 {a0,n} は有理コーシー列なのである K0∈N が存在して p,q≥K0⇒∣ap,0−aq,0∣<20(=1) となります。そして同様に、{ak,n} は有理コーシー列なのである Kn∈N が存在して p,q≥Kn⇒∣ap,n−aq,n∣<2−n(=n times[(1,2)]⋅ ⋯ ⋅[(1,2)]) となります。
こうして得た Kn を用いて候補となる有理数列
rn:=aKn,n
を定めます。
ここで、 rn がコーシー列であることを示します。
任意のϵ∈Q>0 に対して 2−M<4ϵ となる M∈N が存在します。
すると、 n,m≥M かつ l≥max{Kn,Km} の時
∣rn−rm∣=∣aKn,n−aKm,m∣≤∣aKn,n−al,n∣+∣al,n−al,m∣+∣al,m−aKm,m∣<4ϵ+∣al,n−al,m∣+4ϵ
となります。
ここで {[{ak,n}k∈N]}n∈N は実コーシー列なので、ある N∈N が存在して、
n,m≥N⇒[{∣al,n−al,m∣}l∈N]<[{4ϵ}]
となり、実数の順序の定義を用いると、ある lˉ≥max{Kn,Km} が存在して ∣alˉ,n−alˉ,m∣≤4ϵ+4ϵ とすることができます。 lˉ を使うと n,m≥max{M,N} の時
∣rn−rm∣<ϵ
より {rn} はコーシー列です。
Mが存在する理由
証明
2−M<4ϵ⇔4ϵ⋅2M>1 であり、 M に関する数学的帰納法で 2M>M が示せます。
- M=0 の時
1>0 より成り立ちます。
- M=1の時
2>1 より成り立ちます。
- M=k(≥1) の時に成り立つとすると
2k>k
- M=S(k) の時、
2S(k)>2⋅k≥k+1=S(k)
以上より 2M>M が成り立ちます。
有理数のアルキメデス性より、任意の ϵ∈Q>0 について
0<M1<4ϵ
となる正の自然数 M を取ることができます。
よって、
4ϵ⋅2M>4ϵ⋅M>1
で、 2−M<4ϵ が成り立ちます。
収束すること
そして 実コーシー列 {[{ak,n}k∈N]}n∈N が [{rn}] に収束することを示します。
ここで実数列が [{rn}] に収束するというのは以前の定義により
∀[{ϵk}]∈R>0∃N∃δ∃K s.t. n≥N,k≥K⇒∣ak,n−rk∣+δ<ϵk
と言い換えられます。もしうまく N,K,l を選ぶことができれば
∣ak,n−rk∣=∣ak,n−aKk,k∣≤∣ak,n−al,n∣+∣al,n−al,k∣+∣al,k−aKk,k∣
とすることができるので、そのような選び方を考えます。
まず ϵk を下から抑えたいので [{ϵk}]>0 という条件を等号を含まない定義に基づいて言い換えると、ある ϵˉ∈Q>0 と M∈N が存在し、 k≥M⇒ϵˉ<ϵk となります。
先の議論により 2−Nˉ<4ϵˉ となる Nˉ∈N が存在します。
また同様に {[{ak,n}k∈N]}n∈N は実コーシー列なので、ある N′∈N が存在して、
n,k≥N′⇒[{∣al,n−al,k∣}l∈N]<[{8ϵˉ}]
となり、実数の順序の定義を用いると、ある l≥Nˉ が存在して ∣al,n−al,m∣≤8ϵˉ+8ϵˉ とすることができます。
よって、 N=max{Nˉ,N′},K=max{M,N},δ=4ϵˉ とすると、 n≥N,k≥K について
∣ak,n−rk∣+4ϵˉ<(4ϵˉ+(8ϵˉ+8ϵˉ)+4ϵˉ)+4ϵˉ=ϵˉ<ϵk
より {[{ak,n}k∈N]}n∈N は [{rn}] に収束します。
おわりに
お疲れ様です。以上をもって実数を定義することができました。我々が普段当然のように使っている実数という概念がいかに非自明な概念かが分かったと思います。この記事は極力self-containedになるように書きましたが、最後の方の一部の不等式の証明は書くと説明が煩雑になってしまうので割愛しました。
明日の投稿者は@Takeno_hito、@SAH123、@sorane_yadukiです!
追記:誤字を修正しました